猫がぷいと出て行ったあとの
ソファーのくぼみに触れる
温かさが残っているかと思ったのだが
小さな動物の体温は
すぐに消えていた
出て行った猫を探すことはできない
勝手口に立ち
大声で二度呼んだが
彼の耳には
届かないらしい
雑草や潅木が生い茂り
荒野となった庭を
堂々と
まるでサバンナのライオンのように
猫は歩いていく
そしてどこかに
姿をくらましてしまう
ある朝
猫は帰ってこなかった
前夜足しておいた餌も水も
口がつけられていなかった
ここが彼の家というわけでもなく
私に属すというわけでもない
ある日いつものように
ソファーから立ち上がり
のそのそと眠たげに歩いて戸口を出れば
私のところに
戻ってくる義務は無いのだ
長い草の間を歩く猫を想像する
身動きせず体を固くして
獲物を狙い
スプリングのようにすばやく襲い掛かっては
満足げにそれを食す姿を思い描く
柔らかい草に寝そべり
前足をなめては
丁寧に顔を拭く
そして家のほうを一度だけ振り返ると
隣の草原を目指して
歩き出す
そしてその先の荒野を目指して
そしてその先の荒野を目指して
どこまでも
生い茂る藪の間を抜けていったのだろう
心にさっと風が吹き抜ける
アフリカの温かい風が
遠くまで
遠くまで
吹き抜けていく
ブログランキングに参加してみました。ごらんいただけましたら、ちょこっとこのボタンを押してやってくださいませ。決して悪いことは起こりませんので。
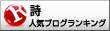
窓際に並べられたクリスマスカードは
もう整然とはしていない
ドミノのように倒れたまま
いつの間にか部屋の風景になじむ
そのうちの一枚を手に取る
二週間ほどのうちに
すっかりしみこんだ楽しい気分を惜しむように
また一枚また一枚と手にとっては
カードを眺める
そしてそれを順番に重ねて
丁寧に分厚い束にする
窓際はクリスマスの暖かさを失い
居心地悪く
殺風景になる
ふっと息を吹きかけると
ほこりが舞い上がる
窓を大きく開けて
外の空気をさっと送り込む
その冷たさにはっと息をのむ
そしてはじかれたように急いで
次の窓も
その次の窓も
全部開け放つ
階段を駆け下りて
寝室にも
子供部屋にも
風を入れる
大きく息をしながら立ち止まり
手の中のクリスマスカードの束に気づく
すっかり寒くなった部屋で
それをどさりと
ゴミ箱に放り込む
12時を廻るころに夜番をする
廊下の電気をつけ
子供部屋に忍び込む
もう布団をけることも
ベッドから落ちることも無くなった彼らの
呼吸を確かめる習慣は
今も続く
電池が切れたかのように
だらんとベッドに寝そべる姿は
数時間前より
ひとまわり小さい
誰かがこっそりドアを開けて
足音を忍ばせて入ってくる
それを知らない無防備さが
心をとがめる
さっと見回し
部屋を出る
明かりを消すかちりという音に
寝返りを打つのが分かる
愛しいものが
夜の暗さに拡がる
闇と交じり合い
私の皮膚に浸透していく
外は限りない星空
今宵も月は
幸福の影を
くっきりと映し出す
あなたを他の人にとられる前に
私達が出会っていればと思う
今ならどうってことのない年の差も
その頃の私達には
大きく感じられたことだろう
まだ恋愛を夢見る頃に
二人が出会い
最初の恋人であったならと思う
そうすればすんなりと
何一つややこしいことなく
当たり前に結婚していただろう
結婚するまでには
たくさんけんかをし
嫉妬し嫉妬され
何度も泣いたことだろう
結婚してからは
せっせと晩御飯を作っては
深夜まで戻らないあなたを待っただろう
浮気を疑って
こっそりワイシャツの匂いを嗅いだかもしれない
突然激しく
どこかから
笑いがこみ上げてくる
自分の声の妙な音に
さらにおかしさがこみ上げて
ははははと笑っては
はっと我に返る
何年も遠く離れて
会えないことに慣れてしまった
私達の生活を思う
そして自分が案外けろりとしているのに
気づく
さっきあなたと電話をしながら
無意識でティシューで作ったこよりを
拾い上げる
それをゆっくり
丁寧にほどいて
窓の光に透かして見る
あなたの足に
香油を注ぐ
あなたを待つ運命を知る
あなたを失うことを知る
夏の夜の闇に
オリーブの木の下で
石榴がこぼれるように交わった
あの確実な肉体を
湿った肌を
今では
遠くに思い出す
手が届くかと思えば
するりと消えてしまう
ああ
幻のような記憶を
あなたの選ぶ運命を
許そう
わたしに背を向け
群衆に顔を上げるあなたを
許そう
私は立ち上がって
群集に混じり歩く
地面の
一つ一つの足跡をたどり
最期まで姿なく
あなたの後をついて行く
あなたが神の栄光とされ
私から完全に奪われてしまっても
あなたが救う世にあって
私だけが救われなくても
かまわない
あなたの体温を分かち合った
この血の流れる肉体と共に
魂が朽ち果てても
私はもう
かまわない
隣人の庭にざくろの実がなった
殻のように厚い皮が裂け
こぼれるように
赤い実が熟す
それをひとつ分けてもらう
乾燥した固い皮を
包丁に力をかけ二つに割ると
水々しい小さな粒がはじけた
丁寧に薄皮を取り除き
口に入れると
果汁が口の中に溢れる
舌にざらつくような
さらりとした甘さ
いつもざくろ特別な果物のように感じていた
妙な情熱やら
怨念を感じ
ただの罪のない果物に
なぜ心惹かれるのだろうと思っていた
すると隣人は
鬼子母神の話をした
皮は赤子の肌の色
こぼれる赤い実は
赤子の肉
そして滴る無邪気な血
いつ誰が
赤ん坊を食らうことを
ざくろに重ねたのか
汁を口の中にゆっくり含み
かすかな渋さに
赤子の血の味を遠く思い出す
医者に寄った朝
学校の前に車を停めて
娘を下ろすと
ハッチバックをあけ
カーブーツの中からかばんとコートを
自分で取り出した
窓を開け
「ついていこうか。
一人で行ける?」
そう言いかけると、
別の少女が近づいてきた
娘はぱっと顔を輝かせ
その子と話を始める
こちらへは見向きもせず
バイバイすら言わず
並んで学校に向けて歩き出す
その後姿をミラーで見つめ
その無礼さに
わざとらしくチッと舌打ちする
そして
こうして自分は不要になっていくのかと
にんまりと笑って
ギアをバックに入れる
昨夜の雨がやみ
太陽が輝いた秋の日の午後
庭を歩く
日は傾き
風はぴたりとやみ
木も枝も草も
息を潜め
秋の静寂に耳を済ませる
猫が一匹
畑の隅に座る
土の匂いを嗅ぐわけでもなく
獲物を狙うわけでもなく
ただ草原のかなたを見つめている
季節の変わり目を感じ取るように
しっとりと広がった空気を
身になじませる
わかってるよ
心が凛としてるのだろう
この美しい時間を
ささやかにでも
取っておきたいのだろう
立ち去る私の足元に
猫は音も無く擦り寄る
その一瞬の友情を
